住宅ローン検索・比較・シミュレーション・申込みなら「イー・ローン」
新築購入をはじめ、住宅に関するさまざまな用途にご利用いただける住宅ローン。
イー・ローンなら、低金利の住宅ローンを比較したり、銀行や信用金庫、労働金庫など金融機関の種類ごとに住宅ローンを検索したりできます。
住宅ローンを探すときに便利なランキングやシミュレーションも用意していますので、ぜひ参考にしてください。



イー・ローンで住宅ローン選び!
住宅ローンとは、住宅や土地の購入などに利用できるローンで、住宅や土地を抵当・担保にします。主に銀行や信用金庫、労働金庫が提供しています。
住宅ローンの主な金利体系は、全期間固定金利、固定金利期間選択型、変動金利の3種類があります。全期間固定金利に比べて、変動金利は金利が低いことが一般的ですが、金利上昇リスクを考えて選ぶ必要があります。また、住宅ローンの借入期間は最長35年が一般的で、審査は借入時や完済時の年齢、勤続年数や年収、雇用形態などを基準に実施されます。
イー・ローンでは、日本最大級の住宅ローンデータベースの中から、新築や中古の住宅購入、借り換えなどの目的ごとに住宅ローンを一覧で比較できます。この住宅ローン一覧では、借入金額や借入期間、金利体系などの希望条件や、職業や年収などの融資条件による検索機能と、借入可能額や金利などによる並び替え機能を用意しています。また、人気の住宅ローンがわかるランキングも随時更新しています。イー・ローンを利用して、あなたにあった住宅ローンを探しましょう。さらに、住宅ローン選びに役立つ住宅ローン関連の金利推移を確認したり、FPからのアドバイスやシミュレーションを利用することもできます。
付帯保障別の住宅ローンランキング
あなたが必要と考える保障がついたローンのランキングを確認しよう。
-
がん診断100%
がんと診断されたら
住宅ローン残高が0円に -
全傷病保障(全疾病保障)
すべての病気やけがによって、
引受保険会社が定める状態となった場合に
住宅ローン残高が0円に -
月次返済保障
入院や就業不能など、
引受保険会社が定める状態である間、
毎月の返済額が0円に
付帯保障を自由に選ぶこともできます。
付帯保障別の住宅ローンランキングを見る2026年2月の住宅ローン金利は?
イー・ローンに掲載している住宅ローンを対象とした、金利タイプ別の金利動向レポートです。
※各金融機関の適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定されます。
- 変動金利
- イー・ローン掲載商品の2月の変動金利の最低金利は、前月と同じ0.550%です。なお、銀行の変動金利の基準金利も、前月と変わらず2.875%※です。
メガバンクの新規借入分の変動金利(適用金利の下限)も、前月同様、三菱UFJ銀行は0.670%、みずほ銀行は0.775%、三井住友銀行は0.925%となっています。
日本銀行は、2026年1月22日・23日の金融政策決定会合において、政策金利(短期金利)を0.75%に据え置きました。2025年12月に0.25%利上げしてから1ヶ月しか経過していないため、1月の据え置きは市場の予想通りでした。
2025年12月の日銀の利上げ後に、メガバンク3行は、住宅ローンの変動金利の決定に大きな影響を与える短期プライムレート(優良企業向けの1年未満の短期貸出金利)を、2月初旬から0.25%引き上げると発表しました。メガバンクを含め多くの金融機関では、今後、住宅ローンの変動金利を引き上げる可能性が高いと思われます。近いうちに変動金利での借り入れを検討している方は、毎月、金利をチェックするようにしましょう。
日銀の植田総裁は、1月の会合後の会見で「経済・物価情勢の改善に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになると考えています」と述べました。今後も利上げがあるとすれば、住宅ローンの変動金利も上昇していくことが想定されます。
※都市銀行各行の中央値 - 固定金利
- イー・ローン掲載商品の2月の固定金利の最低金利は、固定3年は1.550%(前月比+0.250)、固定5年は1.600%(同比+0.250)、固定10年は1.000%(同比+0.050)と、前月から上昇しました。
2月8日投開票の衆議院選挙を巡って与野党の多くが消費税減税を掲げ、選挙結果にかかわらず財政悪化が進むとの懸念が強まったことなどから、1月は日本の長期金利(新発10年物の国債利回り)が一段と上昇しました。その影響から、メガバンク3行は、前月に続いて、すべての固定期間の金利を引き上げました。
三菱UFJ銀行は、適用金利(下限)を、固定3年2.080%(前月比+0.080)、固定10年2.750%(同比+0.070)、固定20年3.510%(同比+0.070)としました。
みずほ銀行は、固定2年1.850%(前月比+0.150)、固定3年2.100%(同比+0.150)、固定5年2.400%(同比+0.200)、固定7年2.600%(同比+0.200)、固定10年2.750%(同比+0.200)、固定15年3.300%(同比+0.200)、固定20年3.500%(同比+0.200)としました。
三井住友銀行は、固定5年2.500%(前月比+0.200)、固定10年2.850%(同比+0.200)、固定15年3.150%(同比+0.200)、固定20年3.350%(同比+0.200)としました。 - フラット35
- フラット35(借入期間21年以上35年以下、融資比率9割以下)の2月の最低金利は、2.260%(前月比+0.180)となりました。
フラット35を活用して返済中の方は、どの金融機関で借り入れの手続きをしたかどうかに関わらず「住・My Note(読み方:すまいのーと)」というインターネットサービスを利用することができます。このサービスは、独立行政法人住宅金融支援機構が提供しており、借入金額、返済日、毎月返済額、団体信用生命保険の契約内容をはじめとした契約情報の照会や、借入金残高の照会、住所変更等の届出、繰上返済シミュレーション、一部繰上返済の申込み、全額繰上返済(完済)の申込み、住宅ローン控除用の融資額残高証明書や現在の残高証明書などの書類の発行依頼およびダウンロード、住まいのお手入れ情報や家計のお役立ち情報等の閲覧等を行うことが可能になっています。なお、金融機関によって取り扱い可能なサービスが異なります。
私が書きました

ファイナンシャル・プランナー。FPオフィス・ワーク・ワークス 代表。
教育出版社勤務後、2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。「お客様のお金の不安を解消する」をモットーに、1,500件を超える個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を中心に活動。無料メルマガ「生活マネー ミニ講座」を配信中。著作 「自分のお金の育て方」(祥伝社)、「老後に破産する人、しない人」(KADOKAWA中経出版)。
SIMULATION住宅ローンのシミュレーション
かんたん返済額シミュレーション
- 返済総額
-
円
- 借入希望額
-
- 返済期間
-
- 金利
-
人気の住宅ローンシミュレーション
住宅ローンを学ぶ
-
- FPからのアドバイス
-
雑誌・新聞等で活躍中のファイナンシャル・プランナーがローンやお金に関する様々な情報をご提供し、ローンの借り方や返し方などをアドバイスします。
-
- イー・ローン TIMES
-
マネーライターが、今話題の情報からお金に関する疑問まで、あなたの家計にゆとりをもたらす情報を発信します。
-
- ローン大辞典
-
難しいローン用語を分かりやすく説明したローン用語集の決定版!
住宅ローンの賢い借り方
ライフプラン別住宅ローンシミュレーション
私が書きました

ファイナンシャル・プランナー(CFPR)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー。
大学卒業後、教育系出版社に入社、教材・雑誌編集などを担当。その後、独立系FP会社を経て、2000年春より独立系FPとして、ライフプラン全般の相談業務や雑誌・HPのマネー系コラムの執筆などを行っている。
FAQ 住宅ローンの基礎知識
- Q.1住宅ローンとは?
-
A.1
住宅ローンとは、原則として契約者本人が居住するための土地・建物の購入資金として利用するローンのことです。取得する土地・建物を担保に借り入れを行います。
住宅ローンを大きく分けると、民間金融機関が独自で提供している住宅ローンと、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する「フラット35」、財形貯蓄をしている勤労者向けの公的融資「財形住宅融資」の3つがあり、現在は民間金融機関で提供している住宅ローンが主流になっています。融資期間は上限を35年以内と設定している商品が一般的で、融資金額は1億円以内の設定が多いですが、最近では2億円以内とする商品も増えています。金利体系は「変動金利型」「固定金利選択型(固定期間1年~30年など)」「全期間固定型」の主に3種類に分けられます。申込資格や資金使途、対象物件、諸費用などの融資条件は金融機関や商品によって異なるため、よく確認するようにしましょう。
今月の住宅ローン最新ランキングはこちら すべて表示する
- Q.2住宅ローンの使いみちは?
-
A.2
住宅ローンの使いみちは、原則として契約者本人が居住するための土地・建物の購入資金、既存の住宅ローンの借り換え資金です。また、住宅購入時・借り換え時の諸費用や、中古物件の購入時・借り換え時のリフォーム資金も上乗せして借り入れできる商品もあります。契約者本人が居住する場合でも、店舗兼住宅といった併用タイプの住宅や、借地上の建物、セカンドハウスなどの場合には、通常住宅ローンとして借り入れることができない可能性や、借り入れが可能な場合でも条件付きとなる可能性が高くなります。その他にも、金融機関や商品によって細かな資金使途が異なるため、それぞれの条件をきちんと確認しておきましょう。
特徴や目的から住宅ローンを探すならこちら すべて表示する
- Q.3住宅ローンの審査とは?
-
A.3
住宅ローンの審査は、他のローン同様に金融機関によって独自の基準が設けられています。例えば、年齢や就業状況といった「契約者本人」に関する審査に加え、取得あるいは増改築する「物件」の両面から審査を行います。どの金融機関も具体的な審査基準は公表していませんが、一般的に審査のチェックポイントは「安定した収入」「他社での借入状況」「物件評価」などがあげられます。
- 契約者本人に関する項目
-
- 住宅ローン完済時の年齢
- 勤務先・雇用形態・勤続年数・年収などの就業状況
- 他社借入件数・借入総額などの既存ローン状況
- 団体信用生命保険に加入できること
- 物件に関する項目
-
- 建築基準法に基づいて建築されていること
- 店舗兼住宅やアパート併用タイプの住宅でないこと
- 物件評価額が借入希望金額に対して基準を満たしていること
- 床面積が一定以上あること
審査は一般的に「事前審査(仮審査)」と「本審査」の2段階で行われ、他のローンと比べると事前審査の申し込みから融資を受けるまでに時間がかかります。本審査に通過した後、契約書面を交わして契約成立となります。同時に、抵当権設定の手続きのため司法書士立ち会いのうえ、登記するための書類を提出することが必要です。最近では、事前審査が最短1日、本審査は数日と審査自体は迅速に行われる金融機関も増えてきています。しかし、実際に融資金が振り込まれるまでにはさまざまな手続きがあるため、余裕をもって対応しましょう。
住宅ローンを探すならこちら すべて表示する
- Q.4住宅ローンを選ぶポイントは?
-
A.4
住宅ローンを選ぶ際にまず検討すべきポイントは、どの金利体系にするかです。当面の返済額を抑えたい、将来的な金利上昇リスクを抑えたいなど、優先させたい内容を考えることが重要です。
住宅ローンの金利体系は、「変動金利型」「固定金利選択型(固定期間1年~30年など)」「全期間固定型」の3つに分けられます。金利は一般的に固定金利型に比べて変動金利型のほうが低く設定され、「変動金利型」→「固定金利選択型(固定期間1年~30年など)」→「全期間固定型」の順に高くなる傾向があります。「全期間固定型」は、契約時に設定された金利が完済まで変わりませんが、残りの2つは返済期間中に金利が変動します。長く低金利が続いている状況で、変動金利型を選ぶ人の割合は増えていますが、住宅ローンは借入金額が数千万円と大きく、借入期間も20年~35年程度と長くなります。そのため、変動金利型の場合、当初は金利の低いローンを選んだつもりでも、10年、15年と経過していくうちに金利が上昇し、結果的に返済総額が多くなる可能性もあります。返済計画を立てるときには完済までの金利上昇リスクも考えておくことが必要です。
金利体系の他にも、保証料や事務手数料など諸費用の確認も重要です。金利は低いものの諸費用を含む支払総額では高くなってしまう可能性もあります。また、団体信用生命保険の保障内容や、繰上返済の利便性などの商品性もしっかりと比較し、総合的に判断することが大切です。
住宅ローンを金融機関から探すならこちら すべて表示する
- Q.5住宅ローンの返済シミュレーションは?
-
A.5
住宅ローンは一般的に借入金額が大きく、返済期間が長期となるローンです。場合によっては、住宅ローンの返済負担が大きく老後資金の準備ができなくなったり、リタイア後まで返済が続いたりしてしまうケースもあります。無理なく返済していけるよう、将来的な借り入れも想定しながら様々なパターンでシミュレーションをするようにしましょう。
返済額シミュレーション(元利均等返済)
- 3,000万円を金利2.0%で35年間借り入れ
- 3,000万円を金利1.5%で35年間借り入れ
- 3,000万円を金利1.0%で35年間借り入れ
借入金額 金利(年率) 毎月返済額
(元金)毎月返済額
(利息)毎月返済額
(合計)返済総額
(合計)3,000万円 2.0% 49,378円 50,000円 99,378円 41,738,968円 3,000万円 1.5% 54,355円 37,500円 91,855円 38,579,007円 3,000万円 1.0% 59,685円 25,000円 84,685円 35,567,804円 このケースでは、金利が0.5%違うことで返済総額が300万円程度変わっていくことがわかりました。今回は金利タイプを全期間固定金利型としてシミュレーションしましたが、イー・ローンのシミュレーションでは変動金利型や当初固定+変動金利型などさまざまな金利タイプのシミュレーションを行うこともできます。
次に、金利2.0%で借り入れていたものを10年後に金利1.0%の住宅ローンに借り換える場合で、返済総額がどのように変化するかシミュレーションしてみましょう。
借り換えシミュレーション
- 借り換え前(当初借入条件):3,000万円を金利2.0%で35年間借り入れ
- 借り換え後:2,345万円(借り換え時借入残高)を金利1.0%で25年間借り入れ
借入金額 金利(年率) 毎月返済額
(合計)返済総額
(合計)借り換え前 3,000万円 2.0% 99,378円 11,925,360円
(10年間分)借り換え後 2,345万円 1.0% 88,376円 26,512,838円 借り換え前後計 38,438,198円 借り換え前後比較 ▲11,002円 ▲3,300,770円 金利の低い住宅ローンへの借り換えで、毎月の返済額も返済総額も軽減されるシミュレーション結果となりました。借り換え前後の金利や、残存期間によって軽減効果は異なりますので、正確にシミュレーションをするようにしましょう。また、住宅ローンの借り換え時には諸費用がかかります。金融機関や商品により諸費用の金額は異なりますので、その点も考慮して最終的なメリットの有無を確認しましょう。
住宅ローンシミュレーションはこちら すべて表示する
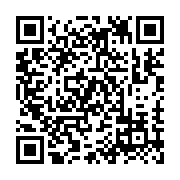
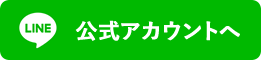
掲載金融機関数・掲載ローン数は最新の情報を、利用実績数は2026年1月現在の累計申込取次ぎ実績を表示しています。
本サイトに掲載しているローンに関するすべての情報はサービス選択時の参考情報を提供することを目的としており、ローン商品の商品性の優劣を示したり、イー・ローンとして特定の金融機関、ローン商品を推奨したりするものではございません。また、特定目的への適合性、正確性、完全性について保証するものではありません。