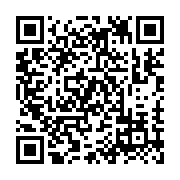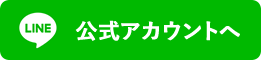第1137回
近年の授業料値上げの要因?2004年の国立大学の法人化を解説
- 国立大学の授業料が値上げされたニュースを見て、不安になりました。子どもは現在、高校生ですが、この先も授業料値上げが続くようだと、学費の負担が重く、受験までに準備できるか心配です。どのように考えておけばいいでしょうか?(会社員・46歳)
- 東京大学が2025年度4月に授業料を引き上げましたが、2018年度以降、首都圏の国立大学では授業料の引き上げが始まっており、ほかの国立大学や私立大学への影響が心配されています。授業料以外にも物価高騰などで家計負担は増加傾向にありますので、余裕をもった資金準備が必要になってきます。教育ローンの利用もひとつの考え方でしょう。

なぜ授業料が引き上げられたのか。国立大学の法人化とは?
東京大学は2025年度4月入学の学部生から、授業料の引き上げを実施しました。国立大学の入学金と授業料は文部科学省令によって、それぞれ28万2,000円、53万5,800円と標準額が決められています。ただし、標準額の20%を上限に各大学で上乗せできることになっており、上限額は入学金が33万8,400円、授業料が64万2,960円となります。
今回、東京大学が引き上げたのは学部生の授業料で、上限の20%の引き上げで64万2960円となりました。修士課程は2029年度入学者から同額に引き上げるとし、博士課程は据え置きということです。
国立大学の授業料などの標準額が決められたのは、法人化された2005年度で、これまで多くの国立大学では標準額のまま据え置かれていました。しかし、物価高騰により光熱費や人件費、設備維持などのコストが増加する一方で、国からの交付金が年々減少し、大学の財政が厳しくなったために引き上げを実施したと説明されています。
そもそも国立大学の法人化は1990年代から議論されており、国の行政組織の効率化を進めるため、行財政改革の一環で2004年に国立大学はすべて法人化されました。それまで国立大学は行政組織の一部門という位置づけで、国立大学の予算は国の予算に組み入れられていました。そのため国立大学の運営費の約半分は国からの交付金でまかなわれていました。
国立大学を法人化することで、大学が主体的に運営を行い、組織改革や民間企業と共同して研究開発を進めることが可能となり、国際的に競争力のある大学、教育の質の向上をもたらすという考え方がありました。一方、大学は自主的な運営ができることと引き換えに、国からの交付金が毎年減額されることになりました。
国立大学の法人化については、さまざまな意見がありますが、法人化から21年経ち、授業料を据え置いてきたものの、前述したように、物価高騰や交付金の削減により、大学運営が厳しい状況になったということです。
大学進学に必要な資金を確認し、貯蓄でまかなえるかチェック
子どもの大学進学に関しては、国立なのか私立なのか、学部は文系か理系かで必要な資金が大きく異なります。子どもの進路を狭めないためには、必要な資金を確認し、早めに準備しておくことがなによりも重要です。
国立大学は文部科学省令の標準額で、入学金と4年間の授業料を合計すると242万5,200円(4年生学部の場合)です。私立大学は入学金、授業料のほか、設備施設費がかかり、文系の4年間の平均額は約400万円が必要となります。
| 学部 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 私立 文科系 | 22万5,651円 | 81万5,069円 | 14万8,272円 | 118万8,991円 |
| 私立 理科系 | 25万1,029円 | 113万6,074円 | 17万9,159円 | 156万6,262円 |
| 私立 医歯系 | 107万6,278円 | 288万2,894円 | 93万1,367円 | 489万539円 |
| 私立 その他 | 25万4,836円 | 96万9,074円 | 23万5,702円 | 145万9,612円 |
※文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
毎月、子どもの教育費の積み立て貯蓄をする、学資保険、こども保険に加入して備える、つみたてNISAを利用するなど、長い期間をかけて準備するのがセオリーです。大学進学が目前であれば、不足額はボーナスから補填するなど、家計のなかで工夫することも大切です。
不足分の手当は、国の教育ローンや民間の教育ローンの利用を検討する
もしも、十分な準備ができていない場合は、さまざまな支援制度を活用し、教育ローンの併用も視野にいれておくといいでしょう。
「高等教育の修学支援新制度」を利用する
文部科学省管轄の学費支援制度で、入学金や授業料を減免し、返済不要の給付型奨学金の支給も用意されています。世帯収入や経済状況などの条件によって支援金額は変わりますが、最大で年間91万円の奨学金を受け取りながら、年間70万円の授業料が減免されます。令和7年度から、多子世帯の学生については入学金・授業料が無償になっていますので、制度内容を確認しておくといいでしょう。
奨学金制度を利用する
各種の奨学金制度を利用するのも選択肢のひとつです。代表的なものは独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。奨学金の多くは貸付型で返済が必要ですが、条件を満たせば、給付型の奨学金を使える場合もあります。給付型奨学金の対象となれば、大学の入学金や授業料が免除または、減額され、返済は不要です。
また、大学独自の奨学金制度を設けている場合もあります。大学によって、給付型か貸与型か、適用基準も異なりますので、進学を希望する大学が決まったら、制度を確認しておくといいでしょう。このほか、自治体や民間企業、団体による奨学金もありますので、幅広い選択肢のなかから家庭の状況や、卒業後の返済条件によって利用するか考えることが大事です。
教育ローンを利用する
教育ローンは、公的機関である日本政策金融公庫、民間の金融機関で取り扱っています。教育ローンは使途が教育関連費に限定されているため、全般的に金利が低いのが特徴です。日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の場合、子どもの人数によって世帯年収の上限額が決まっています。借入限度額は原則350万円(自宅外通学などは450万円)、金利は固定で年2.85%(2025年6月現在)であり、家庭状況によってはさらに低率での貸し付けを受けられます。また、返済期間が最長20年と長いこともメリットです。
民間の金融機関が取り扱う教育ローンは、借入限度額が1,000万円など大きいことが特徴で、学費がかさむ学部への進学や留学などを考えている場合などにも利用できるのがメリットです。金利は変動金利のところが多く、世帯年収などの状況によって適用される金利が決まります。審査スピードが速いので予定外に進学費用がかかった場合にも対応しやすいと言えるでしょう。
奨学金や教育ローンを利用する場合は、親子で返済計画を立て、卒業後に過剰な負担にならないよう注意するようにしましょう。
【参考リンク】
私が書きました

ファイナンシャル・プランナー。
大学卒業後、リクルート(現リクルートホールディングス)に入社。不動産、住宅、マネー情報誌の編集者、マーケティングプランナーを経て2003年独立。フリーランスで各種媒体のエディトリアルアドバイザーを務める。2013年沖縄移住後は、各種WEBサイトに不動産、ライフプラン、マネープランに関するコラムの執筆を中心に活動中。
※執筆日:2025年06月30日